勝鬘院 愛染堂
■場所
大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町
■札所
西国愛染十七霊場 第1番/聖徳太子霊跡 第29番
■由緒
593年、聖徳太子が四天王寺を創建した際に建立した施薬院が、このお寺の始まりらしい。 その後、聖徳太子が人々に勝鬘経の教えを説き、そして勝鬘経に登場するお姫様・シュリーマーラー夫人(勝鬘夫人)の仏像を本堂に安置したことにより、 勝鬘院と呼ばれるようになったらしい。また金堂には愛染明王が祀られており、愛染明王信仰の普及とともに、勝鬘院全体が愛染堂と呼ばれるようになったらしい。 鎌倉時代、鎌倉幕府5代執権・北条時頼から寺領を寄進されたらしい。多宝塔は大阪市内最古の木造建造物らしい。
■参拝日
2014年1月2日
■日記
大阪空襲からまぬがれた大阪市内最古の建造物・多宝塔が残る、勝鬘院 愛染堂に到着!そんなこんなで、山門をくぐり境内へ。 古建築は多宝塔だけかと思ったら、本堂もなかなかの古オーラを放ってました!どうやら、この本堂も古い建物のようで、江戸時代に建てられたものらしいです。 大阪市内で古建築に出逢う事は滅多にないので、否が応でもテンションが上がっちゃいます! しかも本日は、ご本尊の愛染明王さんがご開帳されていたというラッキー! 愛染明王さんまでの距離は2メートルちょいくらいで、遠からず近からずな感じで、いい塩梅の距離感。 そんなこんなで、しばし仏像鑑賞。見た感じ、ベラボーに古い仏像さんじゃないっぽいけど、ご開帳というキーワードに弱いミーハーな私は、 目が焦げるまで仏像さんを目に焼き付ける。 その後、本堂を後にし、大阪市内最古の建造物である、国重文の多宝塔へ。多宝塔前にベンチがあったので、そこに座ってしばし多宝塔鑑賞。 とてもスタイルの良い、カッコいい多宝塔でした!空襲で焼かれなかった事に感謝! その後、座ると腰痛が治ると言われる石に座ったり、愛染めの霊水っていう湧き水を飲んだりしつつ、境内を満喫してました。 ちなみに勝鬘院と書いて『しょうまんいん』と読むらしいです。
■公式ホームページ
■ご朱印■
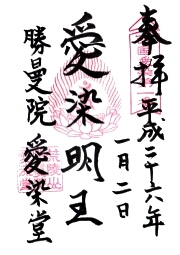
 |
 |
 |
 |
|
■山門■
|
■山門■
|
■中門■ |
■中門■
|
 |
 |
 |
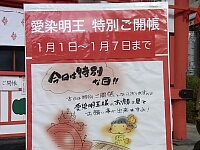 |
|
■金堂■
|
■金堂■
|
■金堂■
|
■金堂■
|
 |
 |
 |
 |
|
■多宝塔■
|
■多宝塔■
|
■多宝塔■
|
■多宝塔■
|
 |
 |
 |
 |
|
■禅堂■
|
■出世白竜明神と願成稲荷明神■
|
■大力金剛尊■
|
■大力金剛尊■
|
 |
 |
 |
 |
|
■愛染めの霊水■
|
■延命地蔵尊■ |
■魚藍観音■
|
■愛染かつら■
|
 |
 |
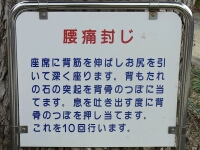 |
 |
|
■腰痛封じの石■ |
■腰痛封じの石■
|
■腰痛封じの石■
|
■腰痛封じの石■
|
 |
 |
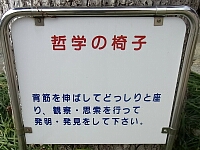 |
 |
|
■哲学の椅子■ |
■哲学の椅子■
|
■哲学の椅子■
|
■哲学の椅子■
|
 |
 |
 |
|
|
■オリジナル瓦■ |
■顔ハメ■ |
■愛染坂■
|
